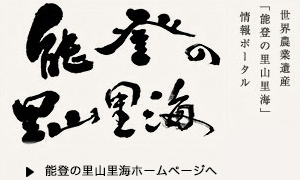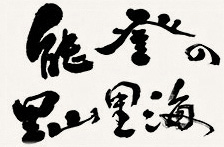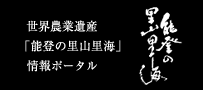名称
妙成寺(ミョウジョウジ)
カテゴリ
歴史・史跡
分類
信仰
年代
11世紀~16世紀
指定状況
・国指定重要文化財「妙成寺本堂」(1950.8)、「妙成寺祖師堂 附厨子」(1950.8)、「妙成寺五重塔 附棟札1枚」(1950.8)、「妙成寺二王門」(1950.8)、「妙成寺書院 附棟札1枚」(1950.8)、「妙成寺鐘楼」(1950.8)、「妙成寺三十番神堂本殿」(1950.8)、「妙成寺三光堂」(1950.8)、「妙成寺経堂」(1950.8)、「妙成寺庫裏」(1965.5)、「山水蒔絵机」(1950.8)、「山水蒔絵料紙筥」(1950.8) ・県指定有形文化財「妙成寺開山堂」(1966.7)、「妙成寺釈迦堂」(1966.7)、「妙成寺三十番神堂拝殿」(1998.2)、「絹本著色日乗上人画像」(1961.11)、「絹本著色涅槃図」(1969.2)、「版本妙法蓮華経」(1983.1)、「妙法蓮華経版木」(1983.1)・県指定記念物「妙成寺庭園」(1970.11) ・羽咋市指定有形文化財「妙成寺総門」(2012.2)、「木造二王像」(1991.2)、「絹本著色日蓮宗絵曼荼羅」(1961.11)、「絹本著色毘沙門天像」(1963.10)、「蒔絵散華丸盆」(1966.2)、「妙成寺古文書・典籍類」(2007.11)、「石造笠塔婆」(1971.3)・羽咋市指定記念物「妙成寺雄滝」(1983.1)
解説
日蓮(にちれん)の孫弟子にあたる日像(にちぞう)が、永仁2 (1294) 年に開創した北陸の日蓮宗本山です。本尊は釈迦如来(しゃかにょらい)と多宝(たほう)如来、山号は金栄山(きんえいざん)。寺伝では、日像が佐渡から七尾へ渡り、京へ向かう道中、この地で槐(えんじゅ)の杖(つえ)を地面に刺し、「杖より根が生ずるなら、汝(なんじ)この地に法華経(ほけきょう)の寺を建立すべし」と、弟子の日乗(にちじょう)に言い残し、ほどなくして根が生えたため、日乗が第二世の住持(じゅうじ)となり、日像を開山に仰いで建立したと伝わります。近世になると加賀藩・前田家に厚く保護され、藩主・利常(としつね)の生母である寿福院(じゅふくいん)の菩提所(ぼだいしょ)として、利常による整備が行われました。前田家御用大工の坂上一門によって伽藍(がらん)が建築され、加賀藩御用大工の坂上一門によって伽藍(がらん)が建築され、国指定10棟、県指定3棟、市指定1棟による寺院伽藍は、県内では他に例が無く、歴史ある古建築を見ることができます。
素材リンク
備考
主
閲覧数
10047回
関連アーカイブ